日食の天然醸造『米みそ』誕生のストーリー

山陰の名勝・大山麓で仕込まれる手作り味噌

その雄大な姿から“伯耆富士”と称される山陰の名勝・大山。
その麓で仕込まれる手作り味噌は、大地の息吹と一緒に育まれています。
米子市から車で10分あまり。
大山の裾野に広がる静かな田園地帯の一角に、大津賀商店さんの工場はあります。
日食の「米みそ」は、ここで作られているのです。
以前は、米子市内の商店街の一角で味噌作りをしていましたが、平成5年にここへ移転。
昭和2年に創業された商店を先代から引継ぎ、同時に味噌製造業の原点となった場所を離れ、新しいスタートを切りました。
「様々な事情から、長年親しんだ旧工場に別れを告げるのは断腸の思いがありましたが、その決断は正解だったようです。」と微笑む会長の大津賀さん。
その理由は?
ここにしかない 大山の水
「丸大豆・米・自然塩といった原料にこだわるのは以前と変わりません。でも味噌の味の決め手は、麹の出来具合にかかっています。
米の蒸し方がポイントなんですね。
その点、ここ大山には、おいしい水がある。
そして、醸造条件に適した気候がある、というわけです。」
なるほど。大山の水のおいしさは有名です。
山陰はもとより、関西地方からポリタンクを抱えて名所の湧き水を汲みに訪れる人たちも少なくありません。
大津賀商店の工場で使う水にしても、明らかに米子市内のそれとはひと味違うのだそうです。
この水が、麹菌の力を借りて発酵する丸大豆を大きくバックアップしているんですね。
米で麹を作り、蒸した丸大豆と自然塩のみで仕込み、約1年間じっくりと熟成させるという「米みそ」。
調味料に頼らず本来の味を引き出すための長年の努力が実った、まさに手塩にかけた逸品なのです。
「私にとって、味噌は人生そのもの。
商売ですから、自分の好みと世間のニーズとの兼ね合いが難しいけれど、一本筋を通したい。これが自分の味なんだ、と。」
味噌への思い入れを語る大津賀さんには、ただ頑なに伝統的な製法にこだわるといった頑固さは感じられません。
味噌作りの奥深さに魅せられ、シンプルな原料からいかにおいしさを引き出すか、というプロセスを楽しんでいる様にも見受けられます。


親子で繋ぐ味噌作りのストーリー
そんな父親の姿勢が息子さんにも伝わったのでしょうか?
自ら進んで後継者を名乗り出た浩司さんは、大学卒業と同時にこの道に進みました。
工場で仕込みを手伝う一方で、フットワークを生かして納品・営業と駆け回り、大津賀商店の三代目として頑張っています。
「伝統にこだわり過ぎず、時代が要求するものを作っていく柔軟性も忘れてはいけない」という大津賀さんにとって、新しい感覚や視野を持つ浩司さんは頼もしい存在と言えそうです。
工場で行われる米麹の仕込み。
蒸しあがった300kgの米を小分けして冷却し、麹菌と混ぜ合わせていきます。
工場内にほのかに酸味のある甘い香りが広がります。
放冷機に広げられた蒸し米に麹菌を混ぜて製麹機に入れ、これを48時間かけて米麹にした後塩を混ぜ、さらに蒸煮した丸大豆と混合し、桶の中で熟成の時を迎えることになります。
味噌作りの各工程をていねいに案内してくれたのは三代目の浩司さん。
「天井を見てください。」という声に顔をあげると、天井と壁一帯に黒っぽいシミのようなものが所々に・・・。
「あれは麹菌で、醸造工場では財産なんです。もっと真っ黒になるまで頑張らないと・・・。」
と瞳を輝かせた三代目の言葉が印象的でした。




ご購入はこちらから
- « 前へ
- 次へ »
2商品中 1-2商品
商品検索
商品一覧
かつお風味だしの素
その他だしの素
調味料、調味食品
- 有機特選濃口しょうゆ
- 味噌
- 酢、みりん、ぽん酢
- 塩、砂糖、はちみつ
- ルウ(カレー、ホワイトシチュー、ハヤシ)
- ソース、ケチャップ、マヨネーズ、バター、ドレッシング等
- 食用油(菜種油、オリーブオイル、ごま油、こめ油等)
食品
- 即席みそ汁
- 缶詰
- 醤油屋さんのラーメンシリーズ
- 麺(ラーメン、うどん、パスタ、焼きそば、蕎麦)
- 麦、小麦粉
- 米飯
- 漬物、ふりかけ
- レトルト(スープ、カレー、ご飯の素、他)
- 乾物
- 香辛料
- 茶、コーヒー
- 飲料
- 菓子
- uchipacシリーズ
- 冷凍食品(クール便配送)
- クラフトビール、酒、おつまみ




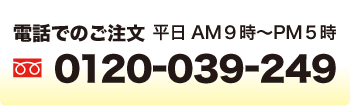




 商品の魅力を紹介
商品の魅力を紹介 食について深く知る
食について深く知る 簡単!レシピ
簡単!レシピ 逸品との出会い
逸品との出会い

